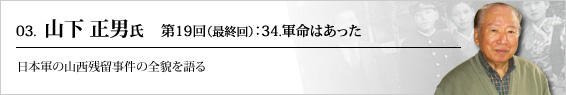 �\�\�R���c�������̎�d�҂������l�����͂��̌�ǂ��Ȃ�܂������B �@��1�R�̑��i�ߐ��c�͎l�Y�ƎQ�d���R�������́A���ꂼ��49�N��48�N�ɋA�����܂������A���̌�Ӊ�̗v���ɏ]���ē��{�����p�`�E�R�̔h����������Ƃ͂���܂łɂ��b���܂����B �@�͖{���Ə��G�A��c�����3���́A1950�N�̏t�ꏏ�ɑ�������k���̎��e���ֈڂ���܂����B��c�͂����Ō��j���Ĕ������A�k���ւ�����2�������ĖS���Ȃ�܂����B��c�������Ă���A���̎����S�̂̐^���������Ƃ��悭�m���Ă����j�ł�����A���������_�ł��c�O�ł��B �@1955�N�A�͖{�Ə��͍Ăё����̎��e���ɑ����܂������A��56�N�͖{�͘V���̂��ߖS���Ȃ�܂����B���{�̈⑰�ɂ́A�⍜�ƂƂ��ɉ͖{�����O���p���Ă����Ԋv�̃W�����p�[�i�u12�@�ݗ��M�l�̗��p�v�̎ʐ^�Q�Ɓj�Ǝ�̈�i�������Ă��܂����B �@���́A56�N6���������ʌR���@��ŋ�18�N�̔������A�����č��ɑ����܂����B�ނׂ̗̊Ė[�ɂ͖��F���c���V�����e����Ă��܂����B �@���́A1964�N3���Ɏߕ�����A4��7�����{�ɋA�����܂����B�A������Ɣނ͎����O�̕��M�̍˂����āA�R���c���ɂ��Ẳ�z�L�w�R���Ɨ���L�x��o�c�Ɋւ���{�𑽐��o�ł��܂������A1985�N�ɖS���Ȃ�܂����B �\�\����ŎR���c�����������ɂȂ�A�R������␟�c�͎l�Y�A�R�������Ƃ������l�������،����ꂽ�̂ł����A�Ō�ɍ���،��ɂ��ďЉ�Ă���������Ǝv���܂��B �@�����Q�l�l�ɌĂꂽ�̂́A�A������̂��Ƃł����A���c��R���������Q�l�l�Ƃ��ČĂꂽ�̂́A���ꂩ��2�N���1956�N�̂��Ƃł����B �@���́A�A������10�����1954�N10��7���A�O�c�@�́u�C�O���E���g�y�ш�Ƒ�����Ɋւ��钲�����ʈψ���v�ɎQ�l�l�̈�l�Ƃ��ď�������܂����B�R���ȂɎc���������R�l��2�l�Ă�܂������A���Z�Ƃ��Ă͎��A������l�͕��m�ł����B���̈ψ���ŁA�A�҂Ɏ���܂ł̊T�v���тɌ��n�ɂ����铯�E�̏��ɂ��ĕ����߂��܂����i���j�B �@ �i���j���̋c���^�́A�C���^�[�l�b�g�Łu�O�c�@��c�^���@��019��@�C�O���E���g�y�ш�Ƒ�����Ɋւ��钲�����ʈψ���@��16���v�Ƃ��Č��邱�Ƃ��ł���B �@���́A�u�R���c���͌R�̖��߂ɂ����̂ł������v���Ƃ������咣���܂����B �@�u�������́A腎��R�R�̋���P�����тɍ��ɏ]�����邱�Ƃ��������܂����B�������A�푈���I����������ɂ���܂��āA���m������ѕ��̊F����́A���ɋA�肽���Ƃ����C���������������Ă��܂�������A�c���������邱�Ƃ͔��ɍ���Ƃ��Ȃ��܂����B �@���̂��߂ɁA���낢��̎�i����@���u�����܂����B���́A��������̕Ґ�������S�����Ă��܂������A�e����ɑ��ẮA��萔�̐l�����c���Ƃ������Ƃ����蓖�Ă��܂����B�����āA�扽�����͏��Z���������炢�A���m�����������炢�A�����ǂ�قǁA�Ƃ����悤�Ɋ��������܂����B �@�����A���ׂĂ̖��߁A�w���͌R����o�Ă���܂����B����ȊO�̖��߂�w���͂���܂���ł����B�v �@���̂��̔����ɂ���āA�œ_�́A���{�R�̒����R���c���͌R�̖��߂ɂ�苭�����ꂽ���Ƃ��A����Ƃ����R�ӎu�i����j�ɂ����̂��A�Ƃ������ƂɂȂ�܂����B �@�ψ���1�l�����}�ؑ����j��c�m�́A�u����͕����ł��邩�A�c���M�l�̈��g���ł��邩�̊�H�ɂȂ����ł���B�������~���͕É��ْ̏��ɂ����̂ŁA�N�����N�����Ƃ̂ł��Ȃ����Ƃ́A���Z�ł��������Ȃ��͏\���킩���Ă����Ǝv���B����ł��R�̖��߂ł���Ƌ������A�����邱�Ƃ��ł���̂��v�ƁA���ɋl�₵�Ă��܂����B �@�u���߂��Ƃ����Ȃ�A�Ȃ��V�c�̖��߂ɏ]��Ȃ������̂��H�v�ƌ��������̂ł��傤���B �@�u�����������I�v�Ǝv���܂����ˁB����Ȃ��Ƃ͎������ɖ₤���Ƃł͂Ȃ��B����́A���������c�����������c�R�i�ߊ���R���Q�d����ɖ₢�l�߂邱�Ƃł͂Ȃ����B�u�㊯�̖��߂͒��i�V�c�j�����߂Ǝv���v�ƒ@�����܂ꂽ�����������A�����㊯�̖��߂ɋt�炦�Ȃ��������Ƃ��炢�A���ČR�Ђ��������Ƃ����ؑ���c�m�Ȃ�悭�킩���Ă���͂��ł͂Ȃ��ł����B �@�����ȁE���{���{�́A�Ȃ�Ƃ����āA�c���͖��߂ɂ����̂ł͂Ȃ��A�u����v�ł��邱�Ƃɂ��悤�Ƃ����Ӑ}�͖��X���X�ł����B�����āA������d�҂����̍����ł������A�u�e���m�͌��n�����̎葱���i�R�Ж����j���Ƃ����v�Ƃ����咣�ɑg�݂��܂����B �@�������A�������畐��E�e����x������A�������ɐ\�����A�������̎w������n�_�ɏW������Ƃ����A����Ȍ��n��������̂���ł��傤���B �@1956�N12��3���A�O�c�@�́u�u�C�O���E���g�y�ш�Ƒ�����Ɋւ��钲�����ʈψ���v�i���j�ɂ����āA5�l�̎Q�l�l���Ă�܂����B �@ �i���j���̋c���^�́A�C���^�[�l�b�g�Łu�O�c�@��c�^���@��025��@�C�O���E���g�y�ш�Ƒ�����Ɋւ��钲�����ʈψ���@��4���v�Ƃ��Č��邱�Ƃ��ł���B �@����1�R�i�ߊ��E���c�͎l�Y�́A���̂悤�ɏ،����܂����B �@�u���͑S���A�҂̕��j���������A������w�͂���������ł���܂��B�v �@�u�e�����̌�������܂��āA���n�A�҂͑S������̂ł���A�����A���ʂ̊�]�������Ďc��l�́A����͂��邢�͂�ނʂ�������Ȃ����A����łȂ�����A�R�Ƃ��Ăł��邾���̐l����A��ċA��Ȃ���Ȃ�ʂ��A�܂��A��ׂ����Ƃ������Ƃ��A�e�����̂����Ȓ��Ԓn�͎c�炸���܂��āA�������ĕ������̂ł���܂��B�v �@�i���c�i�ߊ����e������������Ƃ����̂́A1945�N12���ł������A���̂Ƃ��K��������̏،�������܂��B������3���c�̑�����ł��̌�R���Ɏc���������y�\��E����т͎��̂悤�ɏ����Ă��܂��B�u�����c���ӎv���ł߂�O�̏��a20�N12���A���c�i�ߊ�����������哯�֍s���r���A�k�����������Y�R�ɔ��j����ĕs�ʂƂȂ�A�v������ɂ��������̑���{���Ɉꔑ�����܁A�R�i�ߊ����u������̎c���ӎv�����܂����܂�ʂ���Ƃ����āA�܊p�n�������߂������̎c���ӎv�������������Ƃ͔��Ȃ�ʁv�ƌ����Ďc�����i�𖽂����B�v�i�S���R���c���Ғc�̋��c��ҁw�R���c���̎����x���̓�j�j �@���c�͍���ł���Ɏ��̂悤�ɏ،����Ă��܂��B �@�u�����g�͐�Ɨe�^�҂ł���܂�����A���ڂ̎w���͎R���N���킸��킵���̂ł���܂����A���͂Ƃ��ǂ����܂��āA�����܂ŋA�҂�����̂ł���A�A�҂�����̂ł���Ƃ������j�͌������Ă���������ł���܂��B�v �@�����̍U�h��Ŏ������Ă��鏫����O�ɁA�u2���̋`�E����A��ċ~���ɖ߂�v�ƂԂ��グ�����w�����́g�،��h�͂��̂悤�Ȃ��̂ł���܂����B �@������l�A�Q�l�l�Ƃ��ČĂꂽ�R���������Q�d���́A���̂悤�ɏq�ׂĂ��܂��B �@�u腎��R�R�́A���{�R�̉������Ȃ���A���Y�R�ɑ��ĂƂ��Ă������ł��Ȃ��̂ł��B���̂��߂ɁA�ނ͍ŏ�������{�ɑ��Ď����������������Ƃ����ԓx���Ƃ�܂����A���_��ŏo�Ă܂���܂����B �@�����i���g����ǂ����O�ɔz�z�����p���t���b�g�j�ɏ����Ă������܂��Ƃ���A腎��R�́i45�N�j11�����납��A�Ȃ�Ƃ����{�l���c�����ƍH�삢�����܂����B �@���̊��U�H��Ƃ����̂��A���낢����ւ��i��ւ��܂��āA���Ђ����ɉَq�܂�������Čl�l��q�˂čs���āA�c��Ȃ����Ƃ����悤�Ȃ��Ƃ���邱�Ƃ��������Ȃ��悤�ɕ����Ă���܂����B �@�I���A�R�̋K������O�ƈႢ�܂��āA�ꕔ�ɔ�яo���Ă���ꂽ��������B���������悤�ȓ��{�l�̊��U�ƁA���ꂩ�璆���l�ƁA�ꏏ�Ɋ��U���s��ꂽ�킯�ł������܂��B�v �@�R���́A腎��R���c�������U�������Ƃɂ��ׂĂ̐ӔC�������Ă������Ƃ��Ă��܂��B �@���̓��A�Q�l�l�ɌĂꂽ�c��3���́A�S�X�a�����сE��������A�����]������сE�������A���H�����������сE���R�i�ߕ��t�ł����B3�l�͂�������A�R���͂������Ə،����܂����B �@�S�X�a�����т̏،��\�\ �@�u����Ƃ��t�c�ɘA���ɍs�����Ƃ���A�t�c�i�ߕ����ɓ����c�Ґ����A�����������傪�ł��Ă���܂��āA���c���Q�d�������̎�C�ƂȂ�����c�̕Ґ�������Ă���A���łɓ����c�̕Ґ��}�\�܂łł��Ă���̂������Ă��������܂����B�v �@�u���c������A�N�����͑c�������̂��߂ɁA��1�R�̌�q�땺�Ƃ��Ďc��̂�����A����������悤�ɂƌP�����āA�����c�ɎQ�����܂����B �@�l�l������Ŏc�������̂ł͂���܂���B�v�悳�ꂽ���̂̒��ɁA���������h������Q�����Ă������̂ł���܂��B�v �@�����]������т̏،��\�\ �@�u�R���ɂ������{�̌R���ɂ́A�s�튴�Ƃ������̂��Ȃ������̂ł��B�ǂ����Ă��ƌ����A������������Ȃ���������ł��B���̓��{�̌R�����A���̂܂c��܂����B���X�̍s�������ߌn�������̂܂܂ł����B �@���ߎw���n�����A���{�R���̂܂܂̋@�\�ŁA���m���ʂ����ď���Ɏ���Ŏc���ł���ł��傤���B����͐�ɂȂ����Ȃ��������̂ł���܂��B�v �@�u��قǔz�z���ꂽ�p���t���b�g�i���g����ǂ��z�z�������́j�̒��ɁA�R�i�ߊ��A�R��]���ɗ͊��S�ɓ��n�ɋA�҂�������j���̂�ꂽ�Ƃ����ӂ��ɏq�ׂ��Ă���܂����A���̂悤�Ȏ����͂���܂���B�v �@�u�����̕��c���E�R�c�O�Y�������A���ɑ��āA���O�͕��c�̖��߂Ŏc���ɕK�v�Ȑl�Ԃ�����c��悤�ɖ������āA���͎c�����܂����B�v �@���H�����������т̏،��\�\ �@�u���͏I���A�����ɂ�����R���Q�l�l���k���̕��ʌR�i�ߕ��ɁA�����̓����c���ɂ��ĘA���ɍs���ꂽ�Ƃ��A�k���ɂ����āA�R���ɍs���Ďc��悤�w��������A����ŎR���Ɏc�����҂ł���܂��B�v �@�u���{�R���c�������邽�߂ɁA���a20�N9���ɂ��̕Ґ��@�\�Ƃ��āA���{�R��腎��R�Ƌ����Łu���d�Ёv��ݗ����܂����B11���ɂ͎R���Q�l�l����̂ƂȂ��āA�e���c�̐N���Z���W�߂Ďc���̈Ӌ`����������ƂƂ��ɁA�܂����G��ɑc�������̂��߂Ɏc�����`�����܂����B�v �@�u��1�R�́A�R���Ȃ�5���c�ɑ��A�����c7�c��Ґ����閽�߂��o���܂����B�e���c�ɓ����c�����v�������B����A�R�̑g�D�I�Ȏc�����s��ꂽ�̂ł���܂��B�v �@�u�e���c�́A���Ƃ��Γƍ�3���c�A�ƕ�14���c�̂��Ƃ��́A���̎c��������3�N�ԂȂ���5�N�Ԏg�p���邾���̕���A�e��A���a���������āA���̂܂c�����Ă���Ƃ����ł���܂����B�v �@���������،��ɑ��A���g����ǒ��̓c�ӔɗY�����������́A���̂悤�ɓ����Ă��܂��B �@�u���ǂ��̕��j�ƒv���܂��ẮA�R�̎�]���������̏����ɑ��āA�c������Ƃ������Ƃ𐳎��ɖ��߂��邱�Ƃ͂��蓾�Ȃ����Ƃł���A�ƍl���Ă���킯�ł���܂��B�v �@���̓��قɏے������悤�ɁA�����ȁE���{���{�́A�،��𗠕t���鎖�����������Ȃ��ŁA�����琟�c�E�R����̋��U�́g�،��h���L�ۂ݂ɂ��A�R���߂͂Ȃ������A�Ƃ�����������葱���܂����B���m�݂͂Ȍ��n�ŏ������A���̌㎩�R�ӎu�Ŏc�������̂ł��邩��A���͊֒m����Ƃ���ł͂Ȃ��ƌ����̂ł��B �@�����������̎p���Ə��u�ɂ���āA�펀������F�����̈⑰�⏞���Ȃ���A���҂����������������̑Ώۂ���O����Ă��܂��B  �@��1�R�̎R���c���v��́A�k���ɐݒu���ꂽ���{���{�A�����̏����i�R�����̎��ʂ��A2���쐬���ꂽ����1�������{���{�ɓ͂����Ă��܂����B���{���{�́A���̉A�d�v���m���Ă����̂ł��B �@�����A���{���{���֗^���Ďc�������߂����Ƃ����ɂȂ�A����̓|�c�_���錾�ɑ���d��Ȉᔽ�ł�����A���{���{�Ƃ��Ă������ւ闧��ɂ�����܂��B�ł�����A���{�Ƃ��Ă͉��Ƃ��Ă��u���n�����v�����ƒf�肵�ĉ����ʂ����Ƃ��Ă���킯�ł��B �@�������́A���{�̂��̂悤�Ȕ��f��s���Ȃ��̂ł���ƌ��������Ă��܂����B����́A�P�Ɉ⑰�⏞��R�l�����̖�肾���ł͂���܂���B���{���푈�������ʼn����s���Ă������A�����̎�d�҂������A���㉽���������A�𖾂炩�ɂ��邽�߂ɂ��A���̈��A�d�����͂�����Ɖ𖾂���Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂ł��B �@���̈Ӗ��ŁA���̎����͔����I�ȏ���O�ɋN�����āA���łɏI���Ă��܂����ߋ��̏o�����ł͂Ȃ��A�������̖��𑽂��c�����܂܌��݂Ɏ����Ă��鎖���ł���Ƃ������Ƃ𑽂��̐l�ɒm���Ă��炢�����Ǝv���܂��B�i���j �Q�l����
���̃y�[�W��TOP�@��
|
���m�点 | �v���C�o�V�[�|���V�[ | ���₢���킹 Copyright (C) 2007 OralHistoryProject Ltd, All Rights Reserved. |
