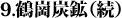 一ヶ月もすると傷も癒えて、まだ痛みはありましたが、私は現場に復帰しました。鶴崗炭鉱では、1グループ15名が1日3交替制で作業していましたから、炭鉱は年中休みなく動いていました。 私たちのグループのリーダーは佐々木さんという元陸軍の下士官だった人で、なかなか統率力のある人でした。私にとって一番勉強になったのは、佐々木さんと私がペアを組んで、発破を仕掛ける作業に携わったことです。鶴崗炭鉱はいわゆる「斜鉱」でしたから、斜層に沿って下の方から発破を装填して火を点けて行くという採掘方法をとっていました。斜鉱ではこのように下から崩していったほうが効率がいいのです。そして、最後の装填を終えるとパッと逃げていくのですが、もたもたしていると最初に仕掛けた発破が爆破してしまいますので、非常に危険な仕事でした。私はまだ少年でしたからさして気に止めなかったけれども、この作業はあまりやり手がいなかったようでした。 あるとき、出口を飛び出す直前に下の方の発破が爆発したことがありました。そのときは、佐々木さんが私の後ろから咄嗟にかぶさってくれて助かりました。この仕事で危ない目に遭ったのは一度だけです。しかし、私たちのいた東山でもこの事故に遭った人がいました。この方は、石炭の砕粒が身体に喰いこんでしまい、目も見えなくなりましたから、惨めでしたね。命は取り留めて日本にも帰国しましたが、いつもハーモニカを吹いていました。 事故とは常に表裏一体の職場でしたから、事故の話は毎日のように聞えてきました。意外と危険であったのは、石炭を坑道口から地上までトロッコで運び上げる作業です。斜層になっているのでワイヤを用いてウィンチで引揚げるのですが、そのワイヤが外れたり切れたりする事故がありました。牽引のワイヤが切れて2千メートルの底まで落ち、犠牲になった人もいました。また、信号のやりかたが悪くて、急に止まったり急に動き出して事故につながることがありました。信号といっても当時のことですから、ちゃんとした設備があるわけではなく、裸線が引いてあって、それに釘のようなものでちょんちょんと触って合図を送っているようなやり方でしたから、危険極まりないものでした。この危険な作業に携わっている人たちを「ドンコ」と呼んでいましたが、「青年突撃隊」のなかの精悍な面構えをした人たちがこの仕事に就いていました。 炭鉱で働いていた人たちにはいろんな人がいました。元軍人だとか、元満映にいた人だとか、何をやっていたか分らない人だとかさまざまでしたが、一人元ヤクザであったような刺青をした体格のいい小父さんがいました。この人が私をいろいろ教育してくれました。炭鉱は私にとっては、またとない「人生道場」でした。 ここで学んだことの一つは、なんでも自分でやらなければいけない、ということでした。掘り出した石炭を坑道口までトロッコで運ぶ作業は、1人で1台のトロッコを押して行くわけですが、大体3分おきぐらいに次々と出てゆくのです。ところが、このトロッコはときどき脱線するんですね。石炭を入れたトロッコの重さは約1トンあるのですが、誰も助けてくれませんから、脱線を自分で復旧させないといけないのです。まごまごしていると、後続のトロッコに追突されてしまいますので、脱線したトロッコの床下に丸太を差込み、肩に担いでレールに乗せる要領を覚えました。しかし、坑道は木で支えてあって、小さく狭く、何時もミシミシ音がし、水も漏れていましたから、非常に怖かったですね。 危険を伴った激しい労働の職場ですから、遊び、息抜きは必要だったのでしょう。私も花札などを教わってやっていましたが、一番楽しみであったのは映画を見ることでした。映画館は東山にはありませんから、鶴崗の町の中心にある映画館まで1時間ぐらいかけて歩いて行っていました。ソ連映画がほとんどでしたが、カラー映画が出始めたころでした。 僕らの住んでいたのは、昔の労働者の長屋だったです。まん中に通路があって、両側に棚床ベッドが並んでいるわけですが、窓はガラスなどありませんから、ムシロのようなものをぶら下げていました。寒かったですね。トイレなど、当然ちゃんとしたものなどありませんから、外でやるわけですが、冬など大のほうは凍って山になっていました。 そんな所でしたが、食べ物だけは素晴らしかったです。白いご飯がちゃんと食べられ、味噌汁もつきました。 ちょうど私がいるときに、新しい宿舎の建築が始まりました。映画館も常設されており、二,三人で一部屋に寝泊りするような構造になっている、それは立派なものでした。こんなところに住めたらどんなに楽しいだろうと思いましたが、私はとうとうそこには入れないで、牡丹江に帰ってしまいました。 私が鶴崗にいる間に、毛利さん(大塚有章)が来たことがありました。大勢の労働者を前にして演説をされましたが、私は一番後ろのほうで聞いていましたけれども、そのときの話の内容も毛利さんのお顔も忘れてしまいました。 鶴崗で私にとって忘れがたいことは、お袋が私を迎えに来たことです。文通はできていましたから、恐らく私は自分が怪我をしたことを手紙で書いたのだと思います。お袋が来る前に、三井さんの部下の人が偵察に来て、傷の具合がどうかとか下見をされ、その報告を聞いてからお袋がやってきました。彼女はまったく中国語がしゃべれませんので、牡丹江から鶴崗まで250余kmの汽車の旅をよく一人で来たものだと思います。 このときも突撃隊の松尾さんが何かとよく世話をしてくださいました。僕ら母子に芋の飴煮をご馳走してくれましたが、あの美味しさは忘れられませんね。 しかし、私にとってはお袋と別れるのは、なんといっても辛かったです。牡丹江に帰って行くとき、小さな背に白いリュックを背負ったお袋の後姿を見ていると、涙が止めどもなく落ちてきて、私は駅の改札口まで見送りに行くことができませんでした。 |
お知らせ | プライバシーポリシー | お問い合わせ Copyright (C) 2007-2009 OralHistoryProject Ltd, All Rights Reserved. |
