


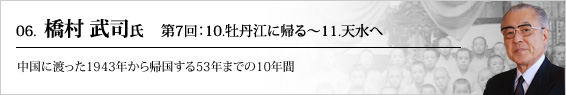

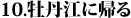

母が迎えに来たこともあって、結局私はまた牡丹江へ帰ることにしました。これは1949年の冬のことで、中華人民共和国が成立して間もない頃のことです。私は17歳になっていましたが、当時の写真を見てもそこそこの体格になっていたと思います。鶴崗では大人に混じって危険な仕事もなんとか一人前にやってきたので、牡丹江へ戻ったときはなんだか凱旋したような気分でした。地下での危険な仕事ができたのだから、太陽の下なら何でもできる、世の中に怖いものなど無いといった高揚感を覚えながら、私はロシア式綿入れ上着に半長靴を履いて“颯爽と”牡丹江へ帰ってきました。
前からの友だちは皆温かく私を迎えてくれました。そんななかで、浦塘(うらとも)君という友人がハルピンにある中国人の学校に行っているという話を聞いて非常に羨ましく思いました。この間私はなにも勉強してなかったので、一種焦りに似たようなものを感じたのですね。(浦塘君とはその後天水にも一緒に行きましたが、彼はそのときにはもう流暢に中国語をしゃべっていました。天水では、彼の勧めで私も中国人の中学校に行くことにしたのです。)
篠原君という友人は、父親が反動分子と批判されて吊るし上げの対象になってしまい、彼が父親の代わりに働いて家族を養っていました。これは気の毒でした。
三井さんはこの後チャムスへ移住しましたので、母も私も一緒に移りました。
私は特にやることがありませんから、独学に邁進しました。なかでも、数学の勉強を一生懸命やりました。代数、三角、幾何とあるなかで、私は特に幾何が好きでした。ご承知のように、幾何というのは、補助線をどう引くかで解答に結びつくという面がありますね。それが面白かったです。松花江の近くの雑貨屋で『幾何のあたま』という本を見つけたときは嬉しさに小躍りしたことをはっきり記憶しています。あのあたりでは本なんかほとんどありませんでしたから。この本は当時の旧制高校の入試問題集でしたが、そのなかには海兵や有名高校の問題が出ており、それらに果敢に挑戦しました。(この本は大事にして日本まで持ち帰りました。)
周囲に先生がまったくいなかったわけではありません。三浦先生とか、早稲田の建築を出た小池さん、北大出の広鰭(ひろはた)さんにはいろいろ教わりました。しかし、大学出の方はほんの数人しかいませんでした。

