




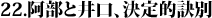

さて、井口一家が呉家村にやって来たその翌日の2月21日には、今度は玲瓏金鉱から老川口と小山口が、呉家村にやってきて、みんなを驚かせた。彼らは中共側から日本への帰国を煽動している張本人とみなされて、玲瓏に送り返されていたのであったが、どうしても関谷先生・井口先生と一緒に日本に帰るのだと言って、強引に玲瓏を発ってきたそうである。
これで、呉家村の日本人は、井口の家族7名と老山口ら2名が増えて、総勢23名になった。
船の交渉に煙台まで行っていた笠原が帰ってきたのは、2月27日である。彼は中国語を話すことができたが、煙台に行ってみて、はっきり解ったことは、政府の出航証明書の無い限り、船は絶対に借りることができない、ということであった。中共政府はそれを百も承知で、彼ら自身にある程度やらせてみた上で、そんなことは絶対できないのだと悟らせようとしていたのである。
ただ、笠原の報告のなかで、一縷の希望が残されたのは、煙台に「聯合国救済総署」なるものがあって、笠原はそこを訪ねてみたのであるが、そこには米国人も2,3人いるらしく(彼が訪ねたときには不在で会うことができなかった)、応対してくれた中国人の話では、全員で煙台に出てくれば、船の手配もなんとかなるかもしれないということであった。
日本への帰還ということが頭の全領域を占領している彼らは、何が何でも煙台に出て、「聯合国救済総署」に縋りつこうと決めた。しかし、彼らに付き添ってくれている中国人の宮は、高経理に報告してくると言って、林家村に帰っていったが、引き返してきたのは3月1日であった。彼が言うには、「目下、煙台を国民党の飛行機が爆撃中であるから、煙台には行けない」とのこと。
実は彼らの行き先は高経理によって、この呉家村から40里(中国里)離れた南花カン村に決められていた。数日後、宮から南花カン村への移動日が3月15日と告げられた。しかし、井口だけはこの村に残すという。彼の監禁問題はまだ結末が付いていないからという理由である。
3月15日の数日前のことである。『招かれざる国賓』には何も書かれていないが、「ダモーイ」には精しく言及されている阿部と井口の関係がある。いま、「ダモーイ」によってそれを復元してみよう。
ある朝、笠原が井口のところに駆け込んできて、阿部がいま莱陽政府宛に密書を書いていて、自分はその中身を見たという。内容は、「自分の替わりに井口が残留することを承諾したから、自分たち家族だけは是非日本に帰してくれ」というものであるという。
井口はすぐに阿部の家に駆けつけた。以下、二人のやりとりである。
「『関屋さん! 私個人のことに関して、一言の相談もなく、勝手なことを書かれては困りますナ』
『手紙は君に見せてから、出す積もりでいたんだ。これだよ・・・読んでみてくれ』
彼は将に封印しようとしていた書状をあわてて引張り出すと、卑屈な笑いを浮かべながら私に渡した。目を通すと、正しく笠原君が知らせてくれたとおりの内容である。
『こんな密書を莱陽政府に送るなんて、私は承服できませんよ』
『いや、皆んなの為だから、井口君一つ我慢してくれんか』
『そんなら、なぜ事前に、私に断ってくれなかったんですか?』
『笠原のやつ余計なせっかいをやったもんだナ。わしは、これを君に見せて、承諾を得た上で送る積もりだったんだよ』
『関屋さん! それじゃ言いますがネ・・・日本人をこの山東省へ招いた張本人は誰ですか? 同胞をこんな極端の苦しみに追い込んだ、元の責任者は一体誰なのですか? 初めに、中共側と約束条件を取決めたのは、関屋さん! あなたじゃないですか。そのご本人が、まっ先に帰国してしまっては、後に残る日本人達は、これから先何を証拠に彼等と折衝して行けばいいんです? それとも、あなたは最初から太華公司の呉宗信君と、帰国についての密約でもあったのですか?』
『いや、何もないさ! まアそれじゃ、この手紙は中止しよう』
『この際申し上げておきますがネ・・・今後、私並びに私の家族は関屋さんご一家と一切の関係を断絶しますから、ご承知下さい』
こうして、私と関屋さんの長い関係は、この異国の空で決裂してしまったのである。」(「ダモーイ」18回)
山東半島が平和な状態で、予定通り科学研究所が建設されていたならば、二人がこんな関係になることはなかったであろう。それもこれも内戦が齎したものである。二人とも大勢の家族を抱えていたために、一時も早く日本へ帰り着きたいという焦りから、このようないがみ合いにまで発展してしまったのであろう。因みに、阿部と井口は、年齢差が9歳ある。阿部は明治31年の生まれで、この年49歳。井口は明治40年の生まれで、40歳であった。
「ダモーイ」は先の二人の会話に続けて、次のように記している。
「その夜――星の美しい晩であったが――私はなかなか寝つかれなかった。思えば、私の大連出発を前にして――君は関屋君の人柄を、よく知っているかネ――念を押す佐藤先生の謎めいた言葉が、冴え返る私の脳裏を幾度となく去来した。」

