




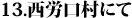

石黒たちが出発後最初に休憩した所は、桃村という村であったが、一緒に来たうちの佐竹、工、宮原の3人とはここで別れた。
石黒たちの一行は山家村という村にひとまず落ち着いたのであるが、この村には工場らしいものがあるわけでもなく、相変わらずなにもやることがなかった。石黒夫人は、「夫たちはまだ仕事が決まらず暇だった」と記している。
石黒たちのグループは、山家村にはそう長くは留まらなかったようで、次に西労口という村に引っ越して行った。ここでもしかし、仕事がなかった。
≪夫たちの仕事がここで始められるのだと思ったが、やはりここも工場一つない辺鄙な山村で、いわば臨時的な腰掛状態であった。はっきりとは感じられぬが中国内戦は愈々熾烈になり、国府軍が山東省へ反撃に出たらしく、科学技術センター建設計画は夢におわりそうであった。≫(『北斗星下の流浪』74頁)
しかし、この村には少し長く腰を落ち着けることになったせいか、『北斗星下の流浪』では西労口での思い出が一番多く語られている。
≪この村に来て、ガンジイと呼ばれている市へ、私たち日本人の奥さん連中が、誘い合わせて買物に行くのが楽しみの一つになっていた。村には日用品を買う店すらないのである。たいてい一週間か十日に一度ぐらいの割で市がたった。みな、中国服を身にまとい、中国のすげ笠をかぶり、大きなリュックサックを背負って出掛けた。吉野さん、佐藤さん、小森さん、横山さん、橋本さん、安孫子さん、森田さん、嫂の花子お姉さん、それに私というようなメンバーだった。
まるで女学生時代の遠足に出掛ける時のようだ。川ぞいの小道をせせらぎの音をききながら歩いた。日本里にして二里位かそれ以上もあったろうか――。途中、二,三回は木陰で休んだ。真赤に熟した柿の木の下はいつも休む場所だった。木陰で弁当をひらき、林檎や梨やすももなどを味わう喜びは格別だった。このように同じ村に住む十家族ぐらいの日本人同志は、ほんとうに心の底から、お互い親しみ合っていた。私の家族は大人数だったから、背負える限り沢山の買物をした。帰る背中のリュックは重かった。≫(同上書、77頁)
先に、同行した人たちの名前のなかに登場せず、ここで合流した人たちとして、吉野、佐藤、安孫子、森田がある。いずれも、中試以外の機関あるいは企業にいた人たちと思われる。
石黒正範「村の名前は覚えていませんが、ある美しい村に入ってしばらく滞在しました。集会場のような広いところに、やることがないので、夜になると大人たちが集まって話をしていました。
ここで学芸会もやった記憶があります。毎日旅をして怖い想いをしまして、やっと先で落ち着けたものですから、「よかったなあ」という感じが子供でもありました。
1週間おきぐらいに母は山を越えて買出しに行っていました。母だけ行っているように書いていますが、僕らもおばあちゃんと一緒に行っていました。途中で弁当食べたりして休みながら帰ってきました。このあたりはのどかな感じが残っています。ここは山東半島のなかで、一番静かに過ごせたところであったと思います。
この村を離れてから、もう1回静かな村へ入った記憶があります。川沿いの村で、ちょっと上流に行くと滝があり、滝壺で泳ぎました。きれいな川でした。熱帯魚のような魚が泳いでいました。安心感があったのでしょう。私のイメージではきれいな記憶として残っています。毎日のようにそこへ行ってはのどかに遊んでいました。」
生活が少し落ち着いてくると、就学児童を抱えている親としては、子どもの教育のことが気掛かりとなってきた。石黒夫人の回想――
≪日本人学校の施設などない中国の寒村で、子供たちの教育のことを真剣に考えねばならないということが私たちの上にのしかかってきた大きい問題であった。(中略)
そこで、同じ村にいる吉野夫人、佐藤夫人に無理にお願いして、正範たちの先生になっていただくことになった。この西労口には四人の就学児童がいた。みんな一年生で、安孫子君と森田さんと、正範の従兄にあたる正弘君、そして正範の四人である。この四人が、吉野先生、佐藤先生に勉強を教わった。四人の児童に対して、二人の先生は、にわかづくりの先生であったが、ほんとうに本職そこのけの立派すぎるぐらい立派な先生だった。
勉強だけでなく、運動会のシーズンには、運動会兼学芸会をやってくださった。生徒はたった四人でも、父兄は日本人の家族ほとんど全員で見に来て下さった。≫(同上書、90頁)
石黒正範「このときの勉強は、教科書があるわけではありませんから、それぞれの母親がワラ半紙の裏に書き写して、それで勉強していたように思います。」

