――山東からの日本人の引揚は、青島を中心に45年の12月ごろ行われたと聞いていますが、いつごろまで続いたのでしょうか。 「46年の初めごろには日本人の引揚が一段落しました。居留民も引揚げ、軍隊の残留していたのも、この頃までにはみな日本へ引揚げて行きました。それで、僕らの活動もひとまず役割を終えた感じになり、いよいよ祖国へ帰って日本の民主化のために一働きしよう、という気持ちになったわけです。 私たちは山東半島の煙台から船に乗りましたが、そのまま日本に向かうつもりでいました。ところが、船が大連を通って朝鮮の新義州に近づくと、満洲にまだ大量の日本人が残っていて、状況は混乱を極めているという話が伝わってきました。これらの日本人を放っておくわけには行くまいということになって、私たちは予定を変更して安東に上陸しました。 安東から北に向かって行軍をはじめて、本渓湖まで来ました。このころソ連軍がどんどん南下していましたから、見つからないようにしなければいけません。その上、奉天(現瀋陽)に国民党の軍隊がすでに入っているとの情報が入ってきたので、行き先も変更して、山の中の行軍に切り替えました。北へ向かって来る日も来る日も行軍してやっと吉林に着きました。ここから新京(現長春)へは汽車で入りました。」 ――満洲にいた日本人は中国本土にいた日本人よりも、やはりひどい状況だったのですか。 「途中で見てきた満洲の状況はどこもひどいものでしたね。新京に着いて、菅沼不二男さんに会ってここでの活動の様子を聞きましたが、ハルピンの方はもっとひどい状況にあるということでした。それで、私たちはすぐハルピンに向かうことにしました。「解放連盟」は満洲へ来てからは「民主連盟」を名乗っていました。ハルピンでは三果樹というところに本拠を置いて、居留民のなかに混じって、彼らの実際の状況を調査することにしました。 ハルピン市内に日本人の子弟が通っていた花園小学校というのがあり、そこは満洲にいた開拓団の人たちの集結場所になっていました。行ってみると、破れた毛布に身を包み、肥料を入れるカマスに寝たりしていて、文字通りの着の身着のままで本当に悲惨な状況でした。隣の人が死んでゆくのに、死に水も与えられないのです。そうすると翌日にはそれを見取った人が死んでゆくのです。あまりにひどい有様なので、私たちはハルピンの街にもどって日本人会の事務所を訪ね、花園小学校の様子を承知しているのかと尋ねたところ、いや、こちらの方が忙しくて行けないのだということでした。 ところが、地段街というところに東本願寺があり、ここにも日本人が集まっていましたが、これはまた対照的なのです。連日、飲めや歌えのどんちゃん騒ぎをやっているのです。彼らの言い分を聞いてみると、「関東軍なんか何だってんだ。我々を置き去りにしてみんな帰りやがって。しかも、軍隊のいたところに行ってみると、倉庫の中には食べるものから飲むものから、あるわあるわ、捨てるほど置いてある。俺たちはこれをどうせ日本には持って帰れないので、それを持ち出してやっているのだ」と言うのです。しかし、難民の悲惨な状況と比べるとあまりに目に余るので、我々はハルピン日本人会に行って、こうした事態は早く何とかするよう申し入れました。事務所は事務所で、毎日難民が引きもきらず相談に押しかけるので、その対応に追いまくられているのが実情のようでした。」 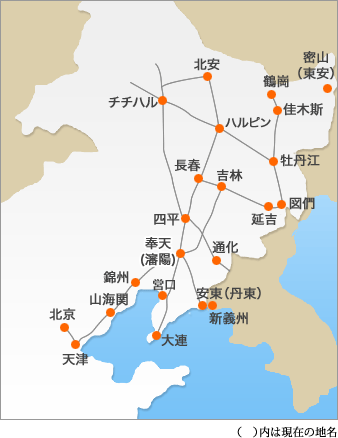 「国民党と共産党の戦闘はすぐ近くで進行していました。松花江には第二松花江というのがあって、ハルピンの南側を流れています。この河は北へ行って本流の松花江と合流し、それが黒竜江へ流れていくのです。この第二松花江を挟んで北上したり南下したりする、いわゆる「三下江南」という言葉がありますが、この河を上がったり下がったりする一進一退の攻防戦が国民党と共産党の間で続いていました。 私たちの仕事は、満洲に留まっている日本人を一日も早く日本に帰国させることでした。私たちはさらに北上するよう指示が出たので、佳木斯(チャムス)に向かいました。佳木斯に来てみると、治安はいっそう悪く、夜になると銃声が聞こえてきました。私たちはお寺の中の1室を借りて、そこで学習会を開き、次の活動の準備に備えました。どういうグループが集まったのかよくわかりませんが、このとき集まった仲間は30人ぐらいいたと思います。指導者は大塚有章さんで、菅沼不二男さんなども講義をしていました。 大塚さんはこの頃「毛利」と名乗っていましたが、このとき大塚さんが話をしてくれたことが記憶に残っています。一人の人が高熱を出して危険な状態に陥ったことがありましたが、水枕が必要だということになり、ある人が「自分が探してくる」と言って出かけていったのですが、結局水枕はなかったといって戻ってきました。別の人がまた「自分が行ってみよう」と言って出かけていった。その人はやはりまともなものは見つけられなかったのだけれども、あるところで穴の開いた水枕を手に入れた。それを自転車の修理をやるところへ持っていって穴を塞いでもらって持って帰ってきた。粗末なものであったが、それを熱冷ましに使ったのです。大塚さんはこの小さなことを例に出して、「本当に苦労を共にした同志であったら、高熱を出している人のことを考えて、どうしても見つけてきてやろう、なんとしても手に入れてやろう、という気になるものです。皆さんもそういうことを頭において活動をやっていってください」と。 こういう話をしてくださったのが、妙に心に沁みていまも残っています。 日本に帰国させる 満洲に留まったまま帰れないでいる日本人を本国に送り返す運動を組織していたのは大塚有章氏である。氏の自伝『未完の旅路』第6巻(1961年)から、この時期の運動の状況を補足しておこう。 日本人を帰国させる作業は、1946年から始まったが、米軍と国民党軍と八路軍が絡んでかなり複雑な様相を呈していた。中国共産党は長春の主導権を握ると、日本人問題を重視する見解を表明したので、それに期待した大塚氏らは中共幹部と一緒に長春へ入っていった。 「長春には約20万人の日本人がいた。私たちは「日本人民主連盟」準備会を結成し、機関誌として『民主新聞』を発行することになった。この『民主新聞』が後に全中国在住日本人のために中央紙の役割を果たすことになった。」(71ページ) 『民主新聞』の編集の中心になっていたのは菅沼不二男氏である。 筒井さんたち日本人民解放連盟の人たちは、東北地方にきてからは、この長春で結成された日本人民主連盟(民連)に合流して活動した。 ところが、蒋介石の大軍が大挙して北上してきたため、民連も民主新聞社も佳木斯に移ることになる。 「東満一帯で活動していた日本人民主連盟の同志たちはほとんど佳木斯に集結した。大きな寺を借り切って毎日学習会が行われた。講師には横川、石田、福田、菅沼など、各々の分野におけるベテランがいたので、充実した学習会であった。」(71〜72ページ) 筒井さんたちのグループは佳木斯で大塚さんたちに合流したのである。 |
お知らせ | プライバシーポリシー | お問い合わせ Copyright (C) 2007 OralHistoryProject Ltd, All Rights Reserved. |
